SOVTEK 5Y3GT(indirect heating)

SOVTEK 5Y3GT(傍熱管仕様)なんですが、何かと似てると思いませんか?
そう、Bendix 6106と構造が似てる。
とは言っても頑固なまでに構造強化されたBendix 6106と比べると作りは劣りますが、
太いカソードとそれを囲む2枚のプレート。
5AR4等のように普通はカソードも2本構造にすることが多いのですが、わざわざ1本カソードにしたのは何故?
6106がスロースターターで音色も独特のものが感じられることからも、これはオーディオ用としても期待できると思いませんこと?

いつから出回っているのか不明ですが、本来の5Y3GTが直熱管であるのに対してSOVTEK製の5Y3GTが傍熱管仕様で電圧、電流とも大きめとなって
いるらしい。
ギターアンプ用途で製造したと思われるので5AR4等と似た扱いになったと思われます。
5Y3を使用するアンプで直熱管故の電圧の立ち上がりの早さを気にする回路構成(直結による真空管の動作や電源のコンデンサー耐圧がシビア)の場合、
傍熱管にしたいが5AR4ほどでもないときに6087(5Y3の傍熱管)や6106(Bendix製の5Y3傍熱管)の出番となりますが、最近は気軽に使
い難くなってしまいました。
そこで、このSOVTEK製5Y3が現行品として白羽の矢が立ったので、実力を調べてみたのが下記。
入力電圧はAC 250V CT(プレートに直列に33Ωを挿入)、出力電流は85mA程(5Y3定格の70%程)、コンデンサーは20μ。
比較対象は5Y3G、6087、6106、5Z4、5T4、5R4GB、5V4G、5AR4を使用。
球
出力電圧 立ち上がり時間
5Y3G
250V
3sec
6087
250V
15sec
6106
265V
90sec
5Z4
280V
15sec
5T4
275V
3sec
5R4GB
260V 3sec
5V4G
270V 15sec
5AR4
290V 20sec
SOVTEK 5Y3GT 285V
20sec
*特性は球のコンディションにもよります
ちょっと甘い結果ですが、SOVTEK 5Y3GTは立ち上がりやや遅め、電圧もハイパービアンスと言えるタイプです。
どちらかと言うと、5Y3より5Z4と同等で、5AR4の電流125mA版と考えて使うと良さそうです。
実際に使用すると、EL34アンプでは整流管のが早く立ち上がって高い+Bがコンデンサーにかかるので、
EL34等のヒーター電流の多いパワー管には向きません。
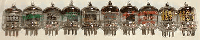
バナー
トップページへ戻る


![]()